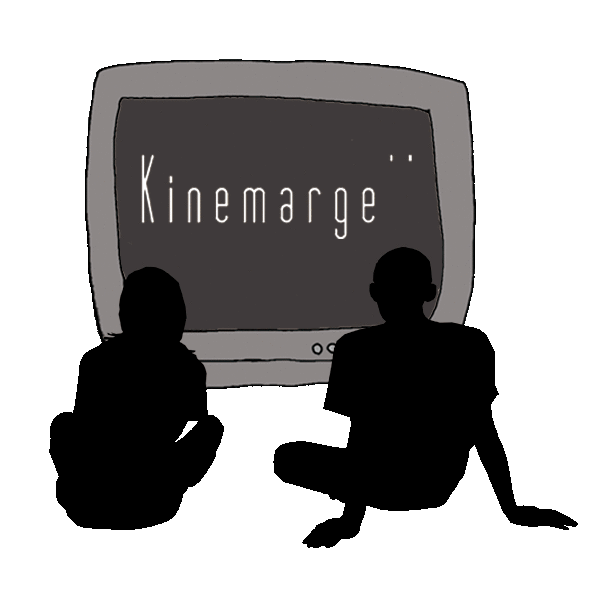彼女はデートに”親友”と名付けた女の子をよく連れてきた。
最初は戸惑ったが、回を重ねると違和感は鈍り、いるのが当たり前になった。
親友の名前は莉子さん。
本当は2人きりがよかったけれど、3人ならではの楽しさもあったので僕は何も言わなかった。
莉子さんが来るようになって10度目の日「”莉子ちゃん”と呼んで欲しい」と本人が言った。
3人で観覧車に乗っている時だった。
彼女は夜景を眺めながらも、そのやりとりをにこやかに聞いていた。
これは彼女の意思でもあるんだなと察し、僕はその通りにした。
翌日、彼女がテレビから目を逸らさず言った。
「あんた最近莉子と喋る時デレデレしてるよな?ほんまにキモイで。」
意味がわからない。
呆れて、何も言えなかった。
その沈黙の先で彼女は「やっぱりな」と言った。
「もう2人でええやん。」と言うと「私には見せられへん2人のなんかがあるんやろ?」と鋭い目つきになった。
莉子さんと僕の関係を疎ましく思いながらも、毎度莉子さんを呼ぶ彼女が理解できなかった。
莉子さんもその空気感を歪に感じ、「私その日用事あるから」と断るようになった。
すると、彼女は空いてる日をしつこく聞いた。
3人とも、もう疲れていた。
数週間後、買い物の帰りに3人でカフェに入った時だった。
彼女が「莉子さ、はよ彼氏つくらんの?」とニヤケながら言い出した。
黙って聞いていたが、あまりにも執拗で、間に入ってしまった。
「なぁ、莉子ちゃんのタイミングがあるんやから、そんなん言うのよくないで。」
できるだけ穏やかに言ったつもりだった。
「はぁ?今莉子と喋ってるねん。まじで黙れよ。莉子は私の友達やから。」
「あんま大きい声だしたら、迷惑や。ってか莉子さんもう無理して来んくて大丈夫やで。ごめんな。ずっと。」
「お前まじできもいな。大人ぶって。やっぱりできてんねやろ?ふたり。」
莉子さんは必死に首を振って「それは絶対にないよ。連絡先も知らないし」と言った。
彼女は自分を制御できなくなった。
そして、大声で汚い言葉を次から次へと僕らにぶつけはじめた。
店員、客、みんながこっちを見ている。
「お前ら、どうせもうやることやってんねやろ、まじきもい、死ね。ほんで、こっち見てるお前らも死ね、死ね、しね。」
汚い言葉を放つ度に、なぜか彼女の体は大きくなり太っていった。
ぶくぶくぶくぶく。
服が弾けた。
それでも彼女は必死に僕らを傷つけようとした。
暴言をやめない彼女の体は店いっぱいに膨らみ、ついに窓ガラスが割れた。
店内に悲鳴が響く。
このままではみんな押し潰されてしまう。
僕はチーズケーキを食べていたフォークで思いっきり彼女のお腹を刺した。
怖かったので、目を瞑った。
ぷしゅーーーっ
空気が抜けきり、静寂が訪れた。
ゆっくり目を開けると、
窓ガラスも周りの人達も何事もなかったかのようそれぞれの時間を全うしている。
僕の目の前には、莉子さんが、莉子さんだけがいた。
ずっと俯いていた莉子さんが、僕の目を見る。
僕は店員を呼び、ふたり分のコーヒーを頼んだ。