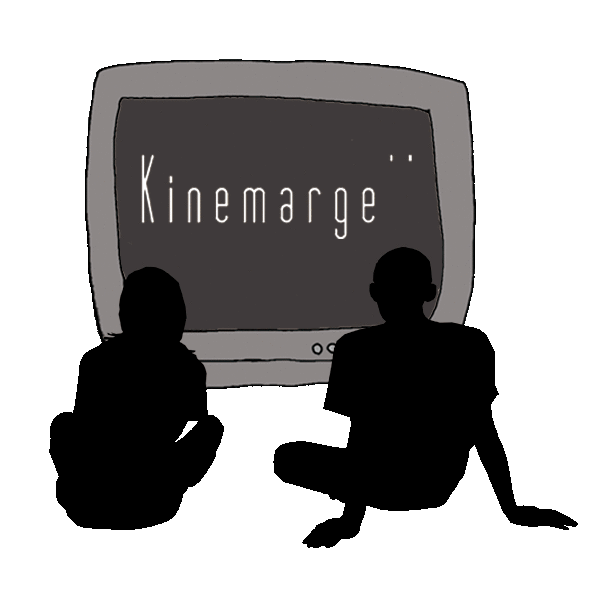セバスチャンは、横たわる自分を介抱する女性をベッドの中からそっと見ていた。
誰を信じ、誰に棄てられるべきなのか
女性は淡々とこなすようにキッチンで湯を沸かす。
「こういうことはよくあるの」
「私がこんなことで狼狽える女にみえる?」
どちらのセリフを言ったとしても、似合う後ろ姿だった。
私は先程まで、酩酊した状態でアンストン通りをふらついていた。
旧友のマシューに酒を呑まされながら付き合う愚痴は、
マシューがいかに女性から好意を寄せられないかという不満だった。
「なあ、もう三十歳だぜ?」と酒が進むほど語気が強まり、挙げ句の果てに泣き出す姿は毎度恒例であった。
マシューには内緒にしてきたが、私に言い寄ってくる女性は昔から多く、彼女が絶えたことはない。
私は母性をくすぐる表情、言動を幼い頃から身につけて歩いてきた。
それはセンスではなく装飾として。
だから、なぜ私が女性から愛されるのかを私自身が一番よく理解していたし、マシューの愚痴は戯言にすぎなかった。
私の母親は私が七歳になってすぐ、愛人と劇的な愛を追いかけた。
もし彼女に再会できた時「愛してもらえるように」という努力が今の私をつくった。
しかし、お酒に酔うとその装飾はいとも簡単に剥がれ落ちた。
マシューと別れた私は、
大通りをはずれ、灯りの減った道をふらふらと歩いていた。
そんな時ポツンと光る夜の花屋がふと目に入り立ち止まる。
その四角い店構えは、母親が一年に一度だけくれた近況報告だけが書かれたポストカードの写真と全く同じだったのだ。
酒に酔う私は感情をコントロールできなくなった
気がつけば花屋の前で子供のように泣き、うずくまっていた。
悲惨な状況に野次馬が集まる中、ある女性の声が聞こえた。
「お騒がせしてすみません。酔っちゃったみたいで。私の弟なんです。」
片腕にオレンジの花束を抱えた女性は、
汁まみれの私の顔をみて「おいで。」と言って手を差し出した。
私は情けない顔で女性の手を掴み、終始何も言わず部屋までついていった。
そして今、彼女のベッドで寝たふりをしているのだ。
なぜ私を怖がらないのだろう。
ブラウンのスパイラルパーマ、淡いグリーンのワンピースに黒のレザージャケットを羽織っている。
それ以外彼女のことを何も知らない。
彼女も私のことを何も知らないが、全て知っているような気もした。
あの時の哀れみのない眼差しは私のためにあったから。
私は誰を信じ、誰に棄てられるべきなのか
徐々に重くなる瞼を意識しながら、初めて誰かのことを深く深く知りたいと思っていた。