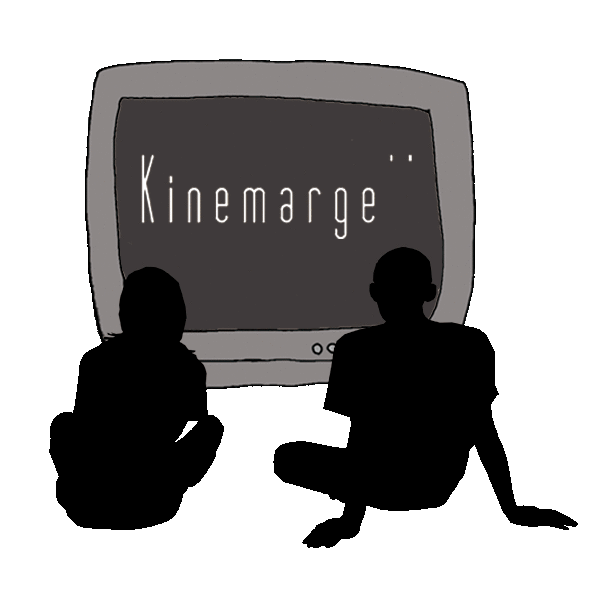バイトの帰り道この信号に引っかかると、右手にパチンコ屋が見える。
今日だって計算されたようにパチンコという文字のパが消えたまま。
面皰だらけの中学生三人組が、あからさまなニヤケ顔で指をさし大声で笑いながら叫んだその声は夜の路地に下品さを装飾した。
彼らはネオン越しにみえる月を知らない
知らない方がいい。
ある程度の鈍感さは生きてゆく上で大切な才能なのだから
今日は酷くどんよりしているからか月が見えないからなのか、平衡感覚を失いかける瞬間が往々にしてある。
瞬きをする度に眠ってしまってもおかしくはないのだ。
原付バイクに跨ったまま
右折可の矢印が灯り、対向車線に車がなだれ込んでくる。
青への準備のためストッパーにしていた右足を浮かせると、スウェットのポケットから携帯が落ちて対向車線にザザザと滑っていった。
僕はパチンコ屋に面する歩道に原付を止め慌てて拾いに走る。
あたふたしすぎ、被っていた半キャップのヘルメットがズレて首がしまり中々痛い光景を繰り広げてしまったが、実際に痛い人間なのだから仕方がないと思うようにした。
心臓が飛び跳ねるようにバクツク。
携帯の液晶が割れていないか確認する。
そしてホームボタンを押してみる。
12分前、新着メッセージ
「電話したんやけど、」
彼女からのメッセージは先ほどまでの焦りとは別種の不安をはらんでいた。
「…もしもし」
「もしもし。今バイト終わったん?」
「もう終わったで」
「お疲れー。なんか色々とうるさいんやけど、どこ?静かな所行ってくれへん?」
「ん、あぁ扉がな、今開いたんや」
「なんの?」
「パチンコパチンコ。してるわけやないで」
パチンコ屋の駐輪場の薄暗さと煙っぽい匂いで僕の不安はとてつもなく大きくなる。
「ん?もしもしー?きこえてる?」
「んー、はいはい」
「あのさ、もう別れよっか」
「また急に、あっさりと」
頭がピリリとなったが感情を隠さないと誰かに怒られると勝手に思った。
「あんた、最近うちと同じタイミングで笑うやろ?好きな物も似てきてさ。でもその事が嫌なわけではないねん。いつもは逆やねんよ。」
「いつも?、ぎゃく?」
「うん。うちが似てきてまうねん。好きな人の好きな物に触れて嬉しくなんねん。同じタイミングで笑っても泣いてもその事に気づかへん、いつもはな。でもな、あんたはちゃうねん。うちの大切な部分、誰にも教えたくない感情に寄りかかってくれる。その代わりに小さく小さくなっていくねん。そのまま明日にはいなくなってしまうんじゃないかって思うのよ。毎日毎日あんたを殺してうちが生きてる気がしてくんねん。でもその考え方ってめっちゃ自己中心的やと思わへん?うちが傷つきたくないからあんたを遠ざけるって。それをわかったうえでもあんたには軽い気持ちで接したらあかん気がする。あんたはうちになったらあかんのよ。うん。絶対に。こんなにも、もぬけの殻やのに色がついてる男は初めてやで。うちをその中に内包したらあんたじゃなくなる。だから、あんたはうちと一緒に居たらあかん。」
「どういうことや…別れたいことには変わらんのか…んー、俺はこれからどうすれば?」
「せやなぁ、明日から自由よ。」
「どっちが?」
「んー、どっちもやな。急にごめんな。ずっと思っててんけどなぁ。月が綺麗な日はちゃんと伝わらん気がして。」
そう言いながら彼女は今まで聞いたことのない笑い方で笑った。
「…」
「ごめんなあ。」
「何が?」
「ぜんぶぜんぶ」
「しゃーないよ」
「ほな今日はもうきるな。」
正直意味がわからなかった。
彼女の言うことも今日という日も。
僕はなにかいけないことをしたのだろうか
わざわざこんな曇った日に言わなくてもいいじゃないか。
そう強く強く思ったのに。
自分のことなのに何故いつもこうなのだろう。
とりあえず今日という一日に疲れた
取り返しのつかない陰鬱さとメランコリーが結びつく前に帰ろうとした途端、影から生まれるように黒猫が飛び出してきた。
その猫はこちらに一瞥もくれることなく僕の行き先である道を歩き出す。
「じぶりみたいなねこやな…」
自然とついていくような流れになり、ネオンの看板が照らす出入り口に辿り着いた。
一人と一匹は自然と同時に立ち止まる。
あぁ…なぜ今日は月がみえない
パはいつになったら戻ってくんねや
ネオンに少し照らされた猫は野良猫にしては毛並みのいい、目の綺麗な黒猫だった。
重たい雲に覆われ有意性を欠いた三日月を黒猫は静かに見上げる。
その瞳の色は月そのものだった。
月が綺麗な綺麗なあの日。
一緒に散歩をしながら「あんたが描く絵をずっとみれる人生はすてきやろうなぁ。もっと色んな人にみられるべきやよ。絶対」と言った彼女の不思議な笑顔がちらついた
今日は子供の頃の泣き方で泣こうと僕はヘルメットをかぶり直した。