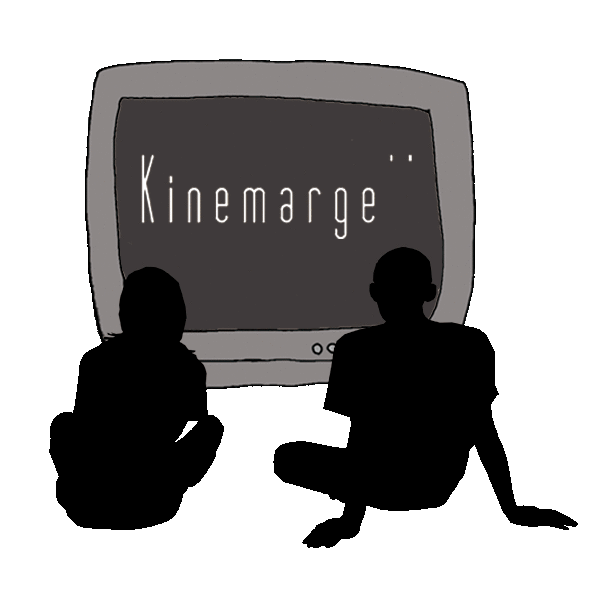愚かだ。
厳かで、愚か。
埃っぽく、かびくさい。
それでも、この小屋は僕と同類だ。
中には錆びたアルミバケツと、謎のロープだけがひっそりと置かれている。
なぜかロープの白さは健在で、不自然だといつも思う。
祖母が亡くなって、5年が経った。
祖父はもっと前にいなくなってしまった。
二人が住んでいた一軒家は、大きすぎることも小さすぎることもなく、親戚の醜い取り合いの末ポツンと残った。
みんな疲れたのだろうか。
諸々の維持費は叔父が払っているらしい。
この小屋は家の玄関から10歩程の場所にある、いわゆる物置き。
家の鍵は持っていない。
時々、この場所に寝袋を持ってひとりで一晩を乗り越えるようになったのは祖母が亡くなってからすぐのことだった。
「またいつでもきなさい。ご飯だけはあるから。」
祖母は帰り際にいつもそう言ってくれた。
今はご飯どころか音もない。
祖母が外出する際かけていた黄みがかった茶色いレンズのメガネを思い出す。
それは祖母を少し怖い印象にさせた。
幼い頃一緒に買い物へ行くと、別人と歩いているみたいで落ち着かなかった。
僕はそのメガネが欲しい。
家の鍵は叔父だけが持っている。
既に誰かが売ってしまっただろうか
小屋のトタン屋根にはポツポツと穴が空いている。
その穴は星のようにも見えたが、本物の星が見たくて今こうして仰向けになっている気がした。
コンクリートは残酷なほど冷たく、寝袋ではどうにもならない硬さだ。
祖母と一緒に星を見たことはたった一度もなかった。
パーカーのフードを被り、紐をぎゅ〜っと引っ張る。
視界はどんどん狭くなり、自分の温もりが頬を覆った。
僕は明日、彼女にプロポーズしようと思っている。