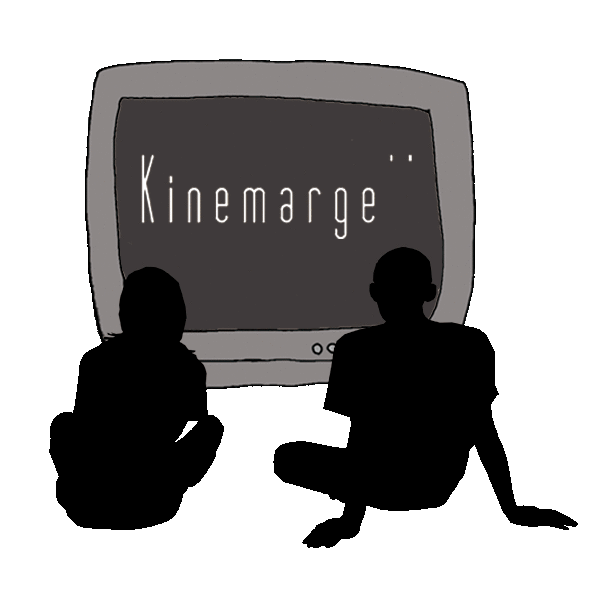“あの人が凱旋ライブをするという”
地元で一番と言われるCDショップに群がる男女の集合体。
その先でギターを抱える華奢な女性…
僕は昨晩、テレビ越しに彼女をみていた。
彼女をみていると、それだけで胸がざわざわ五月蝿いのは、彼女が同い年だからだろうか
それだけなのだろうか
なぜか僕は、彼女の魅力がなんなのかを形あるものに当てはめたかった。
多分、悔しかった。
彼女の人間的な一面を知る度に、強烈な眠気が襲った。
「ワタシもみんなと同じですよ〜」と笑う姿は自分のこれまでの人生を否定された気がしたのだ。
スポットライトがあたるのは彼女だけ
歳を重ね、「テレビあんまみないから」という奴が増えたのは似たようなものなのか?
しかし、今の僕にはまだ希望への渇望があるから辛い。
今朝、何かに取り憑かれたかのよう自転車に跨り、彼女を目指して走ったことが全てだった。
彼女の登場にどよめく群衆の中、
昨晩とは違うギターを持っていることに不安を抱き、
昨晩のギターを覚えている自分を痛々しく感じていた。
彼女は地元に帰って来られたことがどれだけ嬉しいかを話す。
この間もスポットライトは彼女だけに当たり続ける。
観客の照った眼差しは彼女だけに向けられ、当然ながら僕と焦点が合うことはなかった。
人を挟んで彼女がいて
人を挟んで僕がいて
その点では同じだったが、嬉しいことなど何もない。
この数メートルには可視化できない距離があった。
くすぶり続ける自分
友達がいない自分
お金のない自分
家族には長生きしてほしいと思う自分
ここにきた自分
自分も生きているんだと叫びたかった。
ここは僕の地元でもあるんだ、と。
嫉妬、嫉妬、嫉妬。
鳥肌が立つほどの。
それは
しっと。だ
それでも、備え付けられた大きなモニターから目を離せない。
そこには彼女の美しく力強い、どこか儚げでいて、
生に対して楽観ではないが眩しい瞳がアップで映し出されていた。
僕はやっと彼女が持つ才に気付いたのだった。
そして、ここに来た理由がわかった。
ひとりの帰り道、コンビニで吸えないタバコとライターを買った。
カシャーン、カシャーン、カシャーン
自転車をかき鳴らすようにおもいっきり漕いで帰る。
煙でむせかえる僕の人生は彼女になりたいと訴えていた。